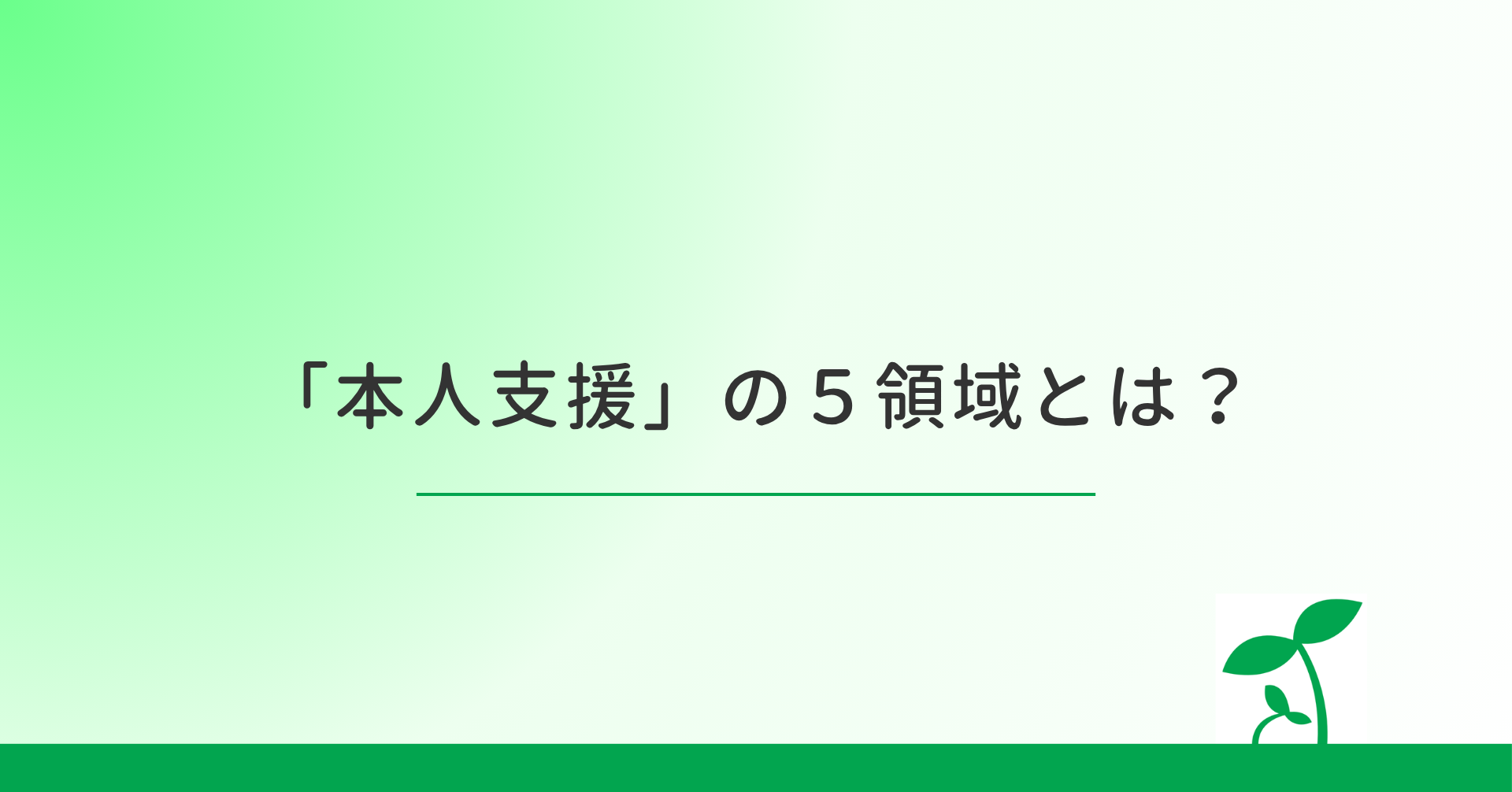児童発達支援や放課後等デイサービス(放デイ)は、障害のある子どもたちにとって「生活」と「未来」を支える大切な支援です。
令和6年度4月の法改正により、個別支援計画「本人支援」の項目において、発達支援の5領域を明記することが必須となりました。
今回は、その「本人支援」および「5領域」についてガイドラインに沿って整理してみたいと思います。
本人支援とは?
児童発達支援は「本人支援」「移行支援」に加え、「家族支援」「地域支援」を含めた総合的な取り組みです。
その中でも中心となるのが、子どもの発達の側面に直接アプローチする本人支援です。
本人支援は以下の5つの領域に整理されています。
- 健康・生活
- 運動・感覚
- 認知・行動
- 言語・コミュニケーション
- 人間関係・社会性
これらはそれぞれ独立しているように見えますが、実際には相互に影響し合いながら発達を形づくっていきます。
5領域と支援内容
1.健康・生活
子どもが心身ともに健やかに生活するための基盤づくりを目指す領域です。
- 健康状態のチェックと異変への早期対応
- 睡眠・食事・排泄など生活リズムの形成
- 食事動作や清潔習慣といった基本スキルの習得
- 生活環境を分かりやすく整える構造化
「生活リズムが安定する → 行動や学習の集中力が上がる」といった相乗効果が期待できます。
2.運動・感覚
体の使い方や感覚の調整を支援する領域です。
- 姿勢保持や基本動作の獲得
- 移動能力(歩行・車椅子利用など)の向上
- 遊びを通した感覚刺激の活用
- 感覚過敏・鈍麻への環境調整
運動や感覚の発達は、自己表現や社会性の基盤にもつながります。
3.認知・行動
「見る・聞く・感じる」から「理解して行動する」までを支える領域です。
- 色・形・数などの概念形成
- 認知過程(情報を選び行動につなげる力)の発達
- 偏食やこだわりなど認知の特性への対応
- 行動障害の予防と適切行動の定着
環境の捉え方や行動の選び方を育てることで、社会生活への参加がスムーズになります。
4.言語・コミュニケーション
ことばや表現方法を広げる領域です。
- 言葉の獲得と活用(発声や語彙の習得)
- 受容・表出の両面での支援
- 指差しや身振りなど非言語的手段の活用
- 読み書きスキルの育成
- 絵カード・機器・手話・点字など多様な方法の導入
「伝えられる」「分かってもらえる」経験が、子どもの自己肯定感につながります。
5.人間関係・社会性
人と関わりながら社会の一員として成長していくための領域です。
- 愛着形成と安心できる関係性づくり
- 模倣やごっこ遊びを通じた社会性の発達
- 一人遊びから協同遊びへ段階的に移行
- 気持ちの調整や行動のコントロール
- 集団参加のルールや手順を学ぶ
子どもが「人と一緒にいるのは楽しい」と感じられることが、社会参加の第一歩です。
まとめ|5領域を意識した個別支援計画へ
放課後等デイサービスにおいて本人支援の5領域は、その事業所の療育を振り返る重要な視点です。
令和6年度以降は、個別支援計画にこの領域を明記することが義務付けられています。
現場で子どもと関わる際にも、
- この支援は「どの領域」にあたるのか?
- 他の領域の視点から振り返ると、どうなるか?
と考えることで、より充実した療育ができるようになります。
子ども一人ひとりの発達を支えるために、5つの領域を意識してチームで取り組んでいきたいですね。